レビュー
本書は、数多くの戦略コンサルタントの中で「常に成果を出し続ける人」と「努力しても頭打ちになる人」の違いを明らかにする一冊です。著者の金光隆志氏は、国内外のコンサルティング現場で長年戦略案件を率いてきたプロフェッショナル。彼が現場で見てきたトップ5%の思考法を、再現可能な形で整理・言語化しています。
序章では、トップ層が他と異なるのは“知識量”でも“分析力”でもなく、「問いの立て方」だと断言します。つまり、問題をどう定義し、どんな構造で考えるかが戦略思考の核心にあるということです。第1章以降では、常識を疑い、仮説を高速で検証し、思考のフレームを広げる具体的なプロセスが紹介されます。
特に印象的なのは、第3章の「戦略思考三種の神器」。MECE(漏れなくダブりなく)、So What/Why So、イシュー・ツリーという基本ツールが、単なる分析手法ではなく“洞察を掘り出すための知的武器”として再定義されている点です。形式的に使われがちなフレームワークを、思考の深化装置として捉え直す視点は非常に実践的です。
後半の「コンセプト思考」や「インサイトドリブン」では、論理とデータだけでは到達できない領域——つまり“意味”や“人間理解”の重要性が語られます。優れた戦略は、事実を再定義し、新しい世界の見方を提示する「コンセプト」から生まれるという著者の主張は、まさにトップコンサルの思考哲学そのものです。
要点
- トップ5%は「情報」より「問いの質」で差がつく
- 問題設定力がすべての出発点
- 常識を疑い、仮説思考を高速で回す
- 思考枠を広げるにはメタ認知と他者視点が不可欠
- 戦略思考の三種の神器:「MECE」「So What/Why So」「イシュー・ツリー」
- コンセプト思考=“意味の再定義”から戦略を生む
- インサイトドリブン=人間理解を起点とする戦略思考
- 戦略とは、世界の構造を再設計する行為である
感想
本書の魅力は、単なるビジネススキル書ではなく、「思考をどうデザインするか」という知的なテーマを真正面から扱っている点にあります。戦略を考えるとは、データを積み上げることではなく、「何が本質的な問題か」「どの視点で世界を捉えるか」を問う営みだと気づかされます。
読んでいて印象に残るのは、“問題の定義力”の重視です。多くの人は課題解決の方法を探しがちですが、そもそも「本当に解くべき問題」を見誤っていることが多い。著者は、トップ5%が常に「問い」から思考を始めると指摘し、そこに成果を分ける決定的な差があると説きます。この部分は、コンサルだけでなく、企画職や経営層にも深く響く内容でしょう。
また、「コンセプト思考」や「インサイトドリブン」は、AI時代の戦略立案にも通じる発想です。データからではなく、人間の行動原理や価値観から洞察を導くという考え方は、定量分析偏重の風潮への強力なアンチテーゼともいえます。特に「コンセプトは世界の見方を変える一文である」という表現には、戦略を“創造行為”として捉える著者の思想が凝縮されています。
全体として、難解な理論を扱いながらも、語り口は平易で、現場に落とし込めるよう工夫されています。ビジネス書にありがちな“精神論”ではなく、実践的な思考の型を示している点も評価できます。
おすすめと評価
本書は以下のような方に特におすすめです:
- 戦略・企画・経営など「考える仕事」に携わる人
- コンサルタント、MBA志望者、事業開発担当者
- 「ロジカルに考える」以上の思考の深さを求める人
- 問題解決よりも「問題発見」に力を入れたい人
読後には、「問いを変えれば、見える世界が変わる」という感覚が残ります。単なるスキルアップではなく、“思考の構造変革”を促す内容であり、読むことで自分の考え方そのものが再設計される感覚を得られるでしょう。
総合評価としては、
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️(5点満点中4.8)
──理論の明快さ、実践性、そして知的刺激の三拍子がそろった名著です。
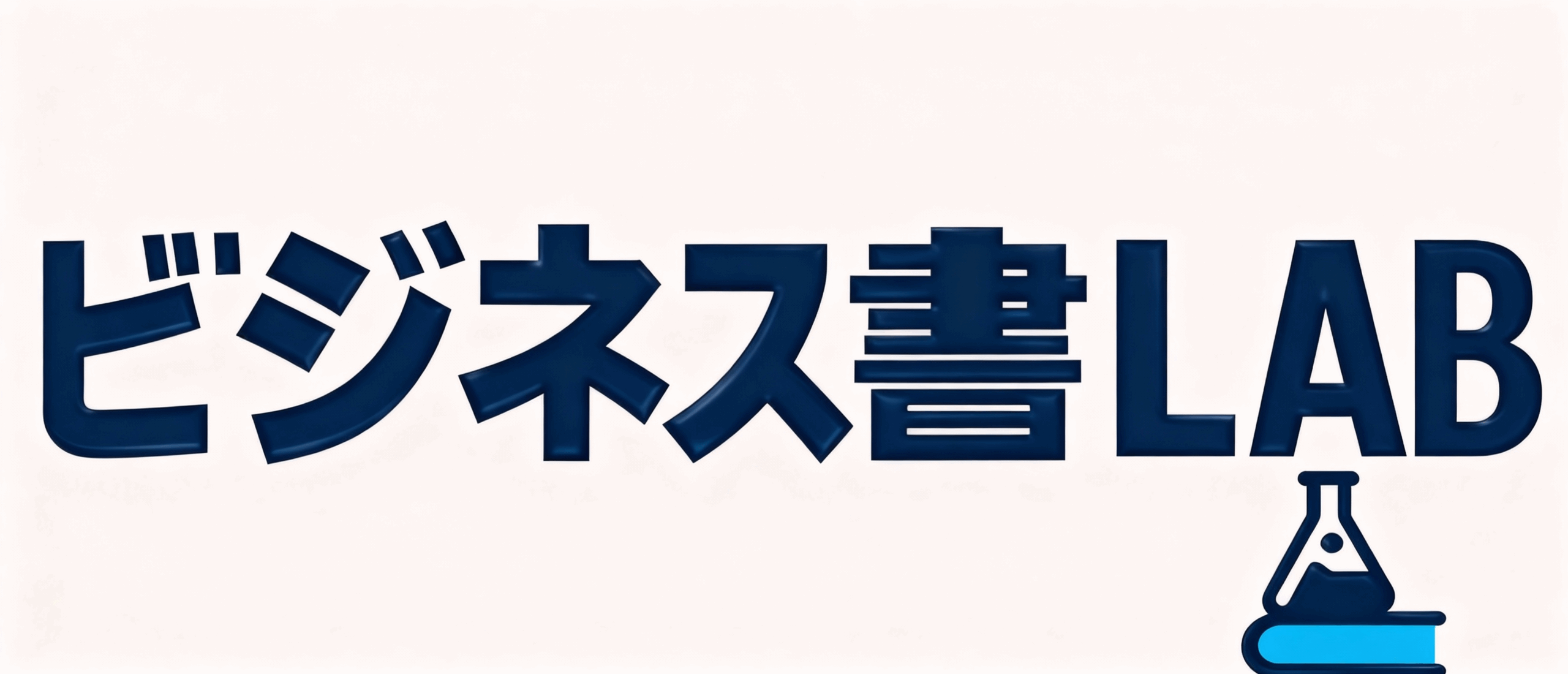









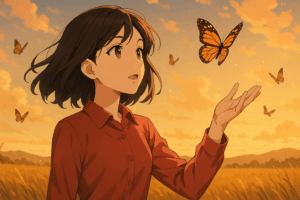

コメント