レビュー
戦略という言葉を聞くと、多くのビジネスパーソンはSWOT分析やポーターの5フォースなどのフレームワークを思い浮かべるかもしれません。しかし本書『ストーリーとしての競争戦略』は、これまでの常識を覆し、「戦略とは語れる“物語”である」と明快に定義します。
著者の楠木建氏は、一橋大学ビジネススクールの教授であり、専門は競争戦略。長年の研究と教育の実践を背景に、数多くの企業事例とともに、戦略を静的な図表ではなく、動的なストーリーとして描くことの重要性を解説します。成功する企業には共通して、思わず人に話したくなるような“ストーリー性”があり、その構造には明確な「コンセプト」と「因果の流れ」が存在するのです。
本書は全7章で構成され、まず戦略を「ストーリー」と捉える本質的な視座を提示し、続いて競争戦略の論理、時間軸の活用、コンセプトの重要性、意外性を持つ施策(=キラーパス)、成功事例の読解法、そして戦略構築の10か条へと展開します。
語り口は平易で読みやすく、難解な理論よりも具体的な事例を通して理解を深められる点も魅力です。また、戦略立案にありがちな“論理のための論理”ではなく、実際に「語れる」「納得できる」戦略の作り方を丁寧に教えてくれます。これは、フレームワークに疲れたすべてのビジネスパーソンに新鮮な視点を与える一冊です。
感想
本書を読んで最も印象的だったのは、戦略を“人に話せるストーリー”として捉えるというコンセプトです。戦略立案というと、データ分析や施策の選択といった「正しさ」を求める傾向がありますが、それだけでは人の心に響かず、社内での共感や納得感を得るのは難しいという現実に気づかされました。
「戦略とはストーリーである」と言われると抽象的に聞こえるかもしれませんが、本書では数々の実例──スターバックス、クレディセゾンなど──を通じて、因果関係の整合性、一貫した選択の流れ、そしてキラーパス的な施策の効用を具体的に語っています。とくに「キラーパス」の考え方は、従来のロジックでは説明しにくい施策の重要性を言語化してくれ、非常に腑に落ちる内容でした。
また、戦略の出発点である「コンセプト」の明確化が、その後の施策のすべてと連動しているという指摘には強く共感しました。コンセプトなき戦略は、どれだけ整った資料があっても“物語”として成立しない。逆に、強いコンセプトがあれば、戦略の流れは自然と筋が通り、現場の実行力も高まる──これは多くの現場リーダーや経営層にとって大きなヒントになるはずです。
一方で、やや抽象度の高い議論や繰り返しの多さに戸惑う読者もいるかもしれません。特にフレームワークによる整理や即効性のあるノウハウを求める方にとっては、消化に時間がかかるでしょう。しかしそれでも、本質的な戦略思考を学ぶにはこれ以上ない教材だと感じました。
こんな人におすすめ
- 戦略立案に携わる経営者・マネージャー層
- フレームワークでは限界を感じているビジネスパーソン
- 新規事業やブランド開発など、“コンセプト”から考える立場の方
- 社内外の共感を得るプレゼン・提案を作りたい企画職の方
- ケーススタディをもとに思考の流れを学びたい人
総合評価
| 項目 | 評価 |
|---|---|
| 内容の深さ | ★★★★★(5/5) |
| 読みやすさ | ★★★★☆(4/5) |
| 実用性 | ★★★★☆(4/5) |
| 独自性 | ★★★★★(5/5) |
| 総合おすすめ度 | ★★★★★(5/5) |
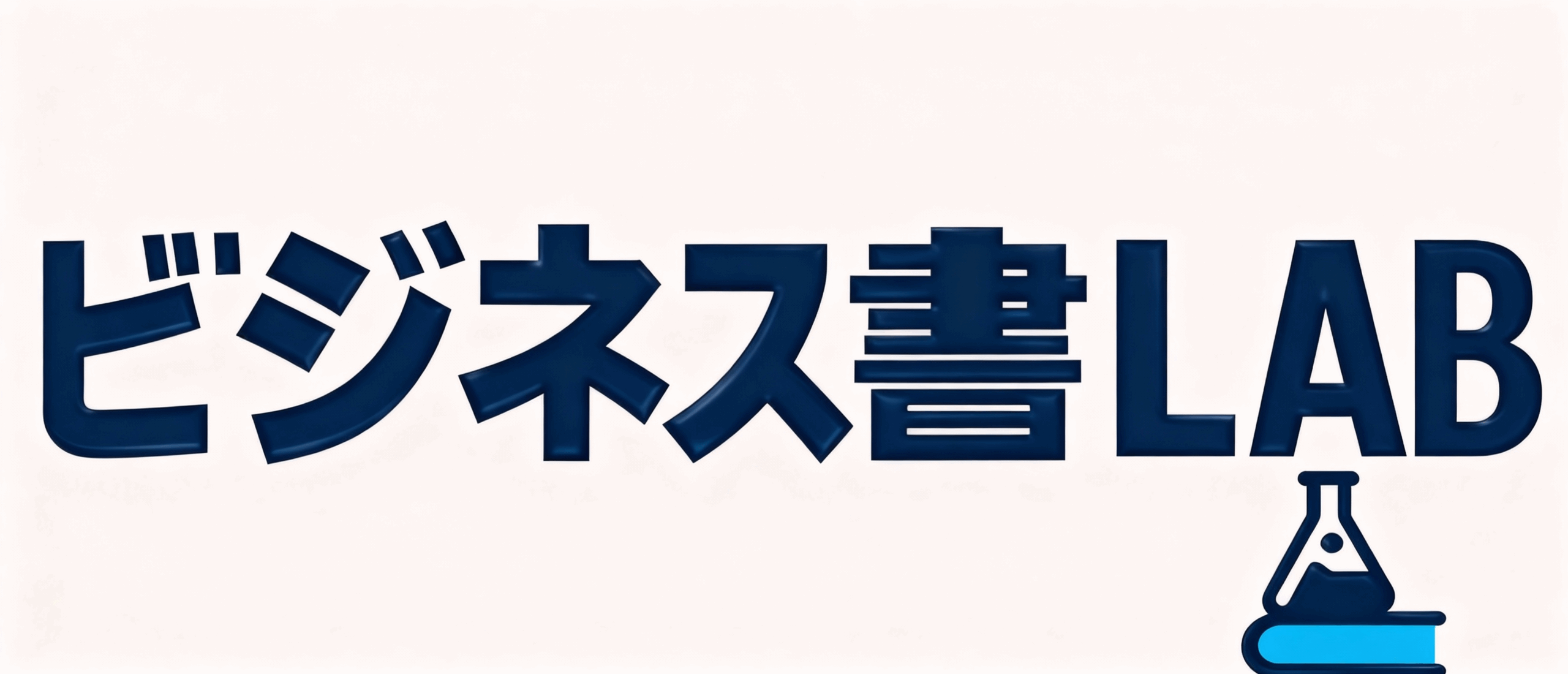
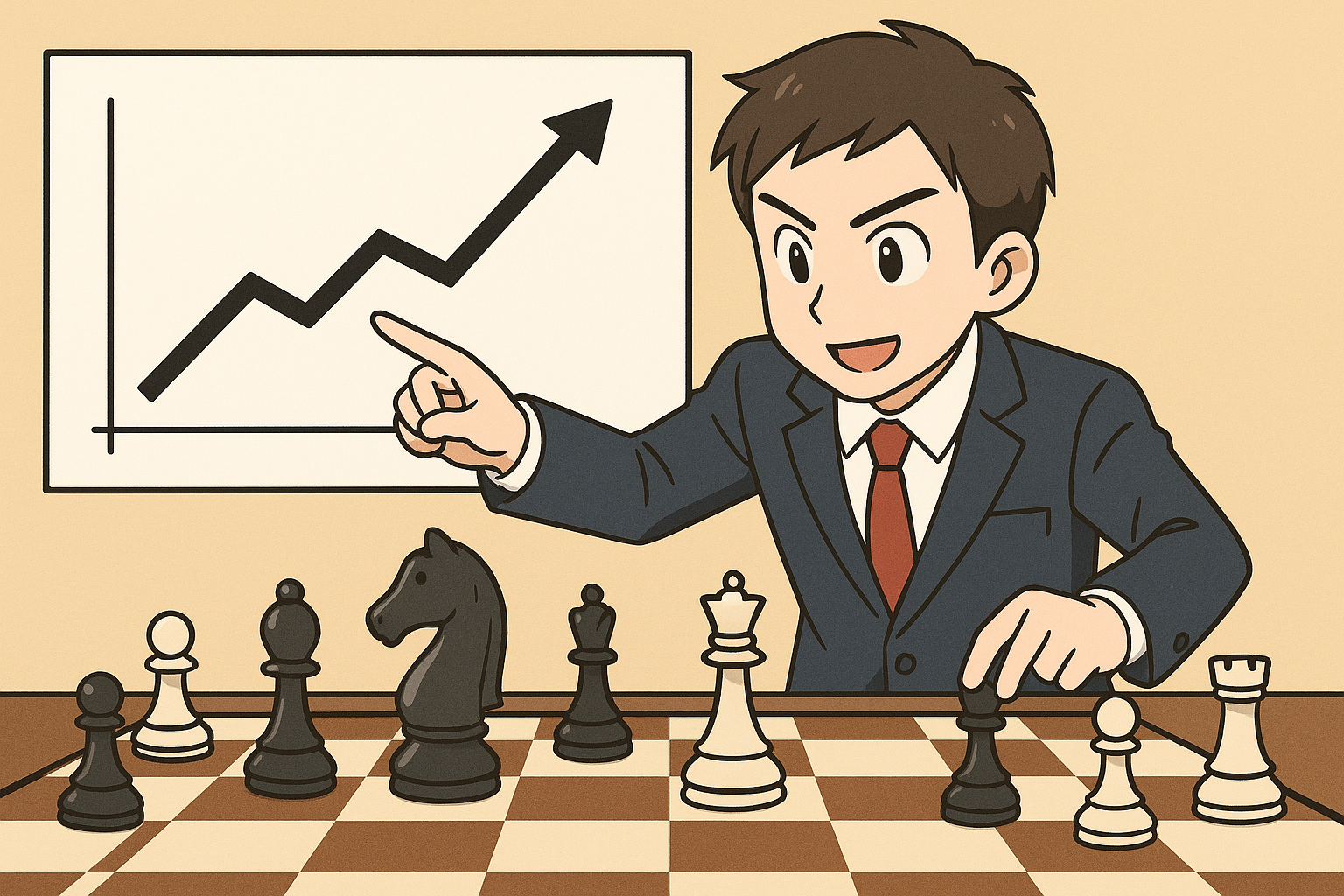

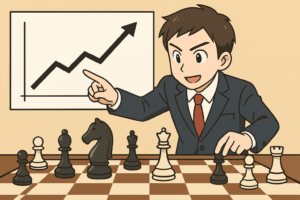








コメント