書籍紹介
「お金って、結局なんなの?」そんな問いに”物語”で答える経済の入門書
『きみのお金は誰のため』は、経済や社会の仕組みを”物語形式”で楽しく学べる、今話題のビジネス教養小説です。
主人公は中学2年生の少年・優斗。ある雨の日、謎めいた女性・七海に導かれ、とある洋館へと足を踏み入れます。そこには「ボス」と呼ばれる大富豪が住んでおり、「この屋敷の価値がわかる者に譲る」と言いながら、優斗に“お金の謎”を問う講義を始めます。
本書の魅力は、読者に難しい経済理論を押し付けるのではなく、疑問や気づきの連鎖を通じて自然と本質にたどり着かせてくれるところ。
例えば、「お金には価値がない」「お金は問題を解決しない」といった逆説的なテーマに対し、トランプやクッキー、ドーナツといった身近な例えで解きほぐしていきます。
読み進めるうちに、お金の本当の役割や格差の正体、社会の持続可能性について、目からウロコの発見が続々。最終章では「私たちはひとりじゃない」という深いメッセージとともに、読後感の温かさが残ります。
著者の田内学氏は元ゴールドマン・サックスのトレーダー。金融の最前線で培った知識を、社会教育へと昇華させた本書は、2024年ビジネス書グランプリで堂々の総合1位に輝きました。
子どもでも読める優しさ、大人にも響く深さ。まさに“すべての世代に贈る経済の教科書”と言えるでしょう。
要点
- お金自体には価値がなく、人々の信頼が価値を生む。
- お金では問題は解決できない。問題を解決するのは“人”。
- 社会全体では「お金を回すこと」が経済を支える。
- 格差は悪人のせいではなく、仕組みの問題。
- 現在の豊かさは「贈与の連鎖」によって支えられている。
- 「お金をどう使うか」ではなく、「誰のために使うか」が問われている。
- 豊かさとは、“お金を得ること”ではなく、“人とのつながり”の中で生まれる。
読後の感想
“お金の話”なのに、読み終わると“人の話”だったことに気づかされる。
本書を読み終えて最も印象に残ったのは、「お金の話」をしていたはずなのに、最終的にたどり着くのは“人間と社会のつながり”だったということです。お金の仕組みを解説するビジネス書は数多くありますが、本書はその一歩先、「お金の先にある価値」まで導いてくれます。
とりわけ印象的だったのは、「みんなが貯金しても社会は豊かにならない」という指摘。経済とは、”循環”によって初めて力を持つ。だからこそ、自分のためだけでなく、誰かのためにお金を使うという選択が、社会全体を豊かにするのです。
また、「格差に悪党はいない」という章では、問題の本質が“構造”にあることを示し、感情論に流されず、冷静に社会を見つめ直す視点を与えてくれました。これはSNSやニュースで“誰かを悪者にする”風潮に対して、強く響くメッセージです。
ラストの「贈与の話」では、胸が熱くなりました。教育、医療、インフラ…すべてが過去の誰かの”贈り物”であることに気づかされた時、自分もその一部として未来へ手渡す側になりたいと、自然に思わされる構成は見事です。
小説としても完成度が高く、中学生から大人まで楽しめる。かつ、読後に「明日からの行動が少し変わる」そんな実用性も兼ね備えた一冊でした。
この本をおすすめしたい人
- お金について「仕組み」から理解したい中高生・大学生
- 「経済は難しい」と思っている社会人全般
- 子どもにお金の教育をしたい親世代
- 投資や資産形成だけでなく、“豊かさ”の意味を見つめ直したい人
- 哲学・道徳・社会課題に興味のある方
評価
| 項目 | 評価 |
|---|---|
| 読みやすさ | ★★★★★(小説形式でスラスラ読める) |
| 実用性・学びの深さ | ★★★★☆(お金の本質を掘り下げる) |
| 説得力・ロジック | ★★★★☆(元金融マンならではの裏付け) |
| 感動・物語性 | ★★★★☆(ラストは心に残る) |
| 誰にでも薦めやすいか | ★★★★★(全年代OK) |
総合評価:4.6 / 5.0
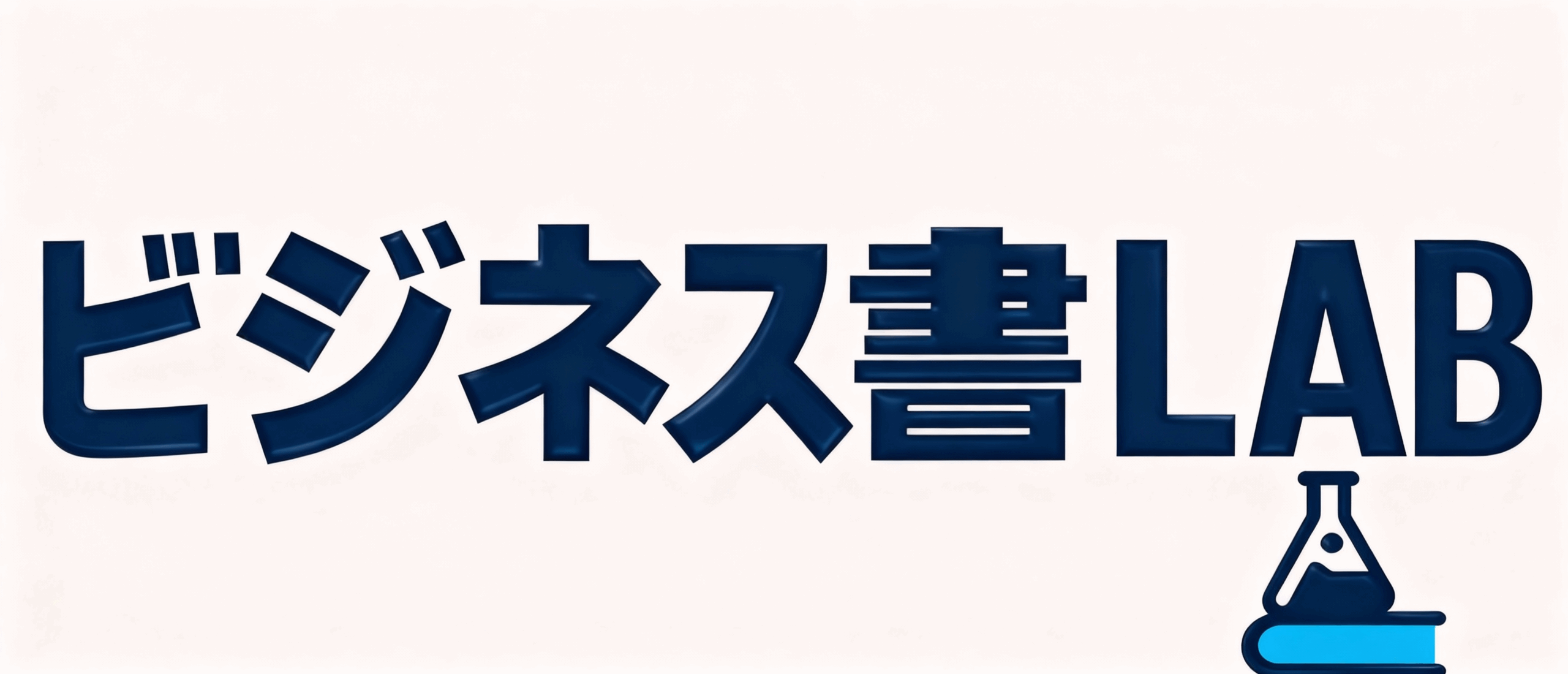
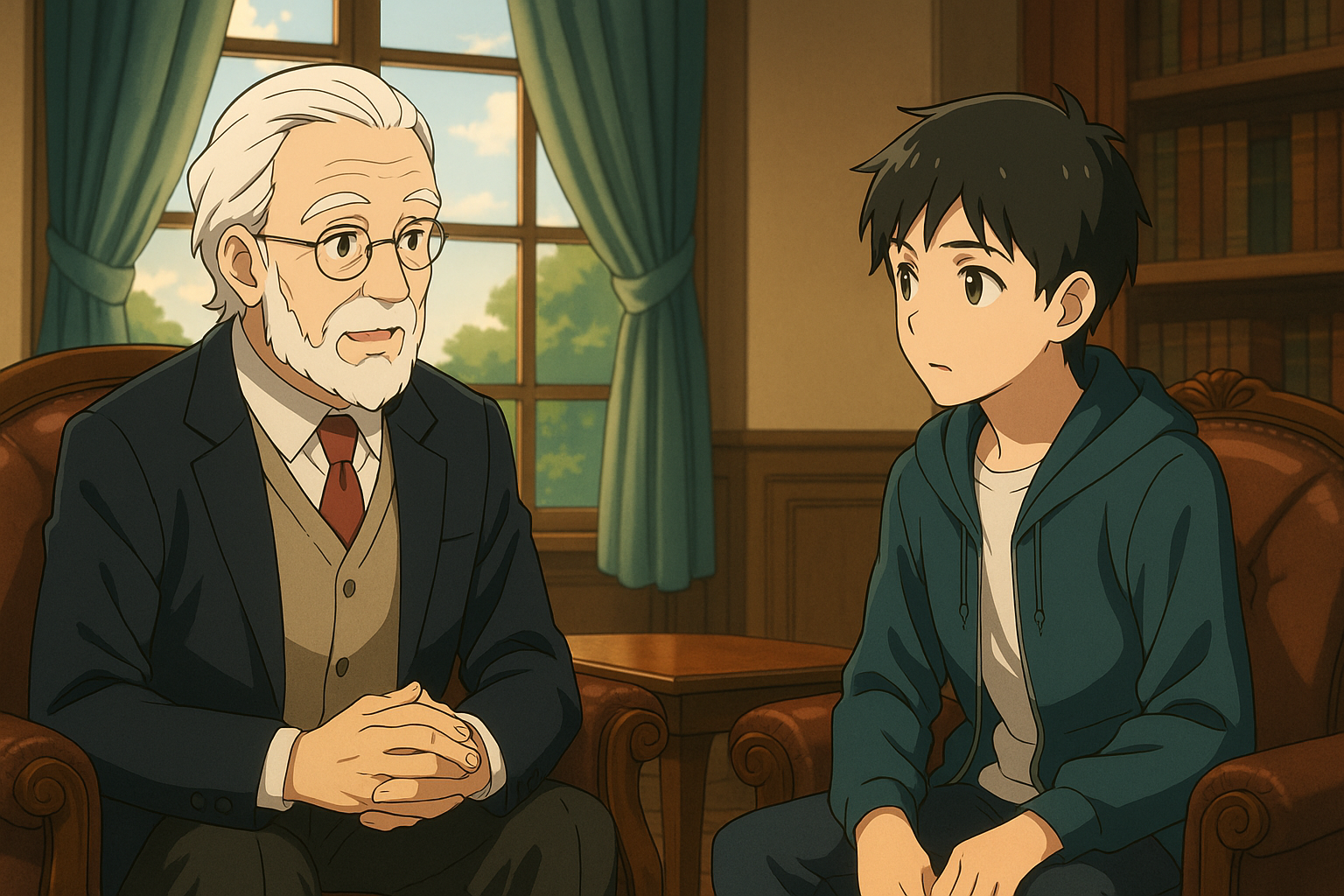

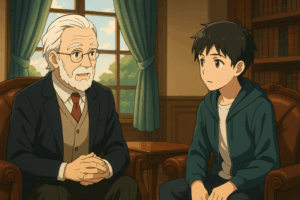








コメント